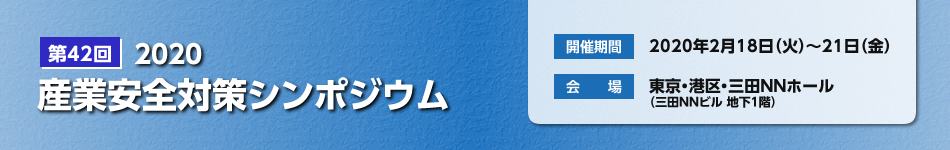2020年2月18日(火)
10:00~13:00
S1
産業安全事故・分析と対策
重大事故の教訓と対策/重大事故の変遷と高圧ガス関連規制の影響
- 高圧ガス事故件数の推移
- 重大事故の変遷と高圧ガス関連規制への影響
- 最近の重大事故
廃棄物における安全問題
- 廃棄物処理での火災爆発の増加
- 火災、爆発のメカニズム
- 廃棄物処理の安全に向けて
日本化学工業協会の保安事故防止への取り組み
- 取り組みの基本方針
- 具体的な実施項目
- 今後の取り進め
安全・安心に対する国民の関心がますます高まる中、各事業者では、安全確保を事業継続の最重要課題の一つとして掲げ、様々な保安管理活動を地道に取り組んできています。しかしながら、高圧ガス事故や危険物施設での事故といった国内産業での近年の事故発生件数は高く推移しており、製造施設のみでなく、物流、貯蔵、廃棄物処理施設など、化学製品のライフサイクル全般にわたっての重大事故の発生が後を絶たないのが現状です。
言うまでも無く、事故防止の基本は、潜在する危険源を適切に発掘することにあります。そのためには、他社の保安事故事例を分析し、事故に至るメカニズムや背後に潜む要因を深く掘り下げ、類似事故の発生防止対策に繋げることは、保安管理レベルの維持・向上に必要不可欠であります。
本セッションでは、製造施設および廃棄物施設での重大事故の傾向や教訓等を各スピーカからご紹介いただくと共に、より具体的かつ効果的な事故事例の活用のあり方などについて議論を行います。
言うまでも無く、事故防止の基本は、潜在する危険源を適切に発掘することにあります。そのためには、他社の保安事故事例を分析し、事故に至るメカニズムや背後に潜む要因を深く掘り下げ、類似事故の発生防止対策に繋げることは、保安管理レベルの維持・向上に必要不可欠であります。
本セッションでは、製造施設および廃棄物施設での重大事故の傾向や教訓等を各スピーカからご紹介いただくと共に、より具体的かつ効果的な事故事例の活用のあり方などについて議論を行います。
2020年2月18日(火)
14:00~17:00
S2
リスクアセスメント、リスクマネジメント
製造現場におけるリスクアセスメントの課題
~リスクアセスメントで事故は防げたか~
~リスクアセスメントで事故は防げたか~
- 重大事故の背景にはリスクアセスメント(RA)の不備がある
- 製造現場は、人・設備が変わってきているが、RAは対応できていない
- どこまでのリスクを許容し、残留リスクにどのように対応しているか
技術経営専門職学位課程 特任教授
石油・化学工場におけるリスクマネジメントの課題と取組み
- 石油・化学工場のリスクマネジメント
- 実務におけるリスクマネジメントの課題
- 課題への取組み(実施体制の強化)
貨物機の運航と安全情報の共有
- 旅客機と貨物機の運航上の差異。航空機の性能いっぱいでの運航
- 不安全事象の調査分析、再発防止策の策定、実施に関する事例紹介
- 諸外国を含む航空業界での安全情報の共有に関する取り組み
リスクアセスメントの目的は、リスクを排除、或は受容できるレベルまで引き下げて、不安全事象の未然・再発防止を図ることです。具体的には、トップマネジメントの下、管理者から現場の作業者までが参加して、リスクアセスメントを計画的に実施し、個人の経験と能力のみに依存せず、リスク管理を組織的・継続的に実施していくことです。しかしながら、その成果を十分に得るのは難しいのが実態です。課題としては、全てのハザード特定が困難な事、リスクゼロを追求するあまり、重大リスクへの対応があまくなりがちな事、経験、知識が乏しい者では、危険性の特定・評価が的確にできない事、等が考えられます。
現場では、自動化の進展で事故が減少する一方、現場での経験、指導の機会が失なわれ、更には、労働人口が減少、働き方改革も進み世代交代(技能伝承)に課題を抱えています。
本セッションでは、この様な現場状況を踏まえて、研究、企業を代表して事例、取り組みの紹介をいただき、『これからのリスクアセスメント&マネジメントの在り方』について考える機会にしたいと思っています。
現場では、自動化の進展で事故が減少する一方、現場での経験、指導の機会が失なわれ、更には、労働人口が減少、働き方改革も進み世代交代(技能伝承)に課題を抱えています。
本セッションでは、この様な現場状況を踏まえて、研究、企業を代表して事例、取り組みの紹介をいただき、『これからのリスクアセスメント&マネジメントの在り方』について考える機会にしたいと思っています。
2020年2月19日(水)
10:00~13:00
S3
最新技術(AI、ビッグデータ)を活用したヒューマンエラー防止とプラント安全
化学プラントにおけるAI・ビッグデータの活用
- 次世代工場構築の背景
- AI・ビッグデータの活用事例
- 化学プラントでの課題
AIを使ったプラントのデータ解析 ー日揮グループ実績紹介ー
- エンジニアリングとAIの重要な関係
- AIによる異常予兆発見・寿命予想等実績
- 展望
交通事故・ドラレコデータを活用した企業の交通安全教育の在り方
- 企業の交通安全教育の現状と課題
- ドラレコ・事故データの融合によるリスクデータベースの考え方
- ドラレコデータを活用した企業の安全教育のモデル
デジタル技術(AIやビッグデータなど)の活用が世界中で広がりつつあり、省力化や生産性の向上などが進んでいます。そして、この技術を産業現場での安全性や自主保安にも適用することが期待されています。セッション3では、その実現に対し、何についてどのように活用できるか、どのような利点が見込めるかなどの観点から、以下の話題を提供します。
(1)化学プラントの実データに対して適用する際のAIとエンジニアリングの重要な関係。異常予兆検知や寿命の予想を行った事例、および、今後の展開。(2)化学産業を取り巻く環境の変化と次世代の工場構築に向けた取り組み。デジタル技術を活用した事例と今後の課題。(3)交通安全教育の現状と課題。ライブレコーダーと事故データを融合したリスクデータベースの考え方。ドライブレコーダーを活用した安全教育のモデル。
これらの話題は、みなさんの産業現場でのデジタル化、高効率化、自動化の在り方などについて議論する格好の機会になることでしょう。
(1)化学プラントの実データに対して適用する際のAIとエンジニアリングの重要な関係。異常予兆検知や寿命の予想を行った事例、および、今後の展開。(2)化学産業を取り巻く環境の変化と次世代の工場構築に向けた取り組み。デジタル技術を活用した事例と今後の課題。(3)交通安全教育の現状と課題。ライブレコーダーと事故データを融合したリスクデータベースの考え方。ドライブレコーダーを活用した安全教育のモデル。
これらの話題は、みなさんの産業現場でのデジタル化、高効率化、自動化の在り方などについて議論する格好の機会になることでしょう。
2020年2月19日(水)
14:00~17:00
S4
レジリエントな防災・減災とその先のあり方
(激甚化する自然災害に備え、乗り越えるために)
(激甚化する自然災害に備え、乗り越えるために)
減災から防災社会の構築
- 想像力の欠如に陥らない防災を
- 減災で良しとせず防災社会を
- 地域防災の担い手育成
地域災害医療コーディネーションの実際とその後の取り組み
- 東日本大震災への対応
- 東日本大震災前の備え
- 東日本大震災後の取り組み
南海トラフ震災を見据えた 社内での備え/地域での備え
- 社内における備え
- 明海地区の災害リスク
- 地域における備え ⅰ救護所設置 ⅱ情報伝達 ⅲインフラ整備
近年、台風、豪雨、地震などの自然災害は激しさとともに発生頻度が増加し、毎年多くの人命と財産が失われています。災害時における事業活動の継続、早期回復は、直後の人命救助はもとより、日本経済の停滞リスクを排除するうえでも不可欠ですが、今日ではあらゆるモノの生産やサービスの提供が複雑な関連性を持つネットワークによって成り立っているため、防災・減災の充実はすべての企業にとって重要な責務と言えます。また、災害に向き合う自助・共助・公助の考え方は企業活動にも当てはまります。
このセッションでは、東日本大震災において最大の犠牲者を出した石巻市において、通常の機能がマヒするなか素晴らしいレジリエンス力を発揮した石巻赤十字病院の事例、防災・減災のための地域企業連携に取り組む豊橋・明海地区の事例から学びながら、激甚化する自然災害を自社のリアルな問題として捉え、地域や社会を支える一員として、今後どうあるべきかを考えてみたいと思います。防災・減災の実効性を高め、その先のあり方を考える機会としていただければ幸いです。
このセッションでは、東日本大震災において最大の犠牲者を出した石巻市において、通常の機能がマヒするなか素晴らしいレジリエンス力を発揮した石巻赤十字病院の事例、防災・減災のための地域企業連携に取り組む豊橋・明海地区の事例から学びながら、激甚化する自然災害を自社のリアルな問題として捉え、地域や社会を支える一員として、今後どうあるべきかを考えてみたいと思います。防災・減災の実効性を高め、その先のあり方を考える機会としていただければ幸いです。
2020年2月20日(木)
10:00~13:00
S5
現場力の強化による安全文化の醸成
チーム医療による現場力の強化から安全文化へ
- チームSTEPPS導入によるチーム力の強化
- 医療安全文化の醸成
- 重要事例検証システムの構築がもたらす効果
工事協力会社との連携による安全文化の醸成について
- 当事業所と工事安全連絡協議会の概要
- 当事業所での工事協力会社員災害発生状況と背景要因
- 工事協力会社と連携した安全への取り組み状況と成果
航空業界における安全管理システムと安全文化の醸成
- 安全管理システムの概要
- 安全管理システムと安全文化
- 更なる安全への取組み
安全文化の成熟度を高め、その波及効果が広く現場に浸透することにより、初めて「現場力」の強化が達成されます。定常・非定常を問わず、作業を高い信頼度で実施するには、個人の力量ばかりでなく、周囲の協働や支援さらには職場の規律への理解や組織の取り組みが重要な役割を果たすことになります。このセッションでは、(1)医療現場における日々の膨大な看護行為を丹念かつ確実に実施していく現場力へのチーム医療・安全文化がもたらす貢献について、(2)大規模プラントにおける協力会社との連携をベースとした現場力の発揮について、(3)航空業界の安全性を飛躍的に向上させた独自の安全管理ツールの活用による安全文化の確立とその将来展望について、以上、たった一つの人的過誤が大きなインパクトを与えかねない3つの代表的な産業において、どのような戦略で安全文化を高め、その結果として、事故・インシデントを最小に押しとどめたかを知り、自事業所への取り込みや展開を考える際に大いなる恩恵をもたらすものと考えます。
2020年2月20日(木)
14:00~17:00
S6
ヒューマンエラー・ヒューマンファクター
ヒューマンファクターの活かし方を考える
- 人間の負の側面と正の側面
- 人間の負の側面に基づいた安全対策
- 人間の正の側面を活かそう
現場社員の「危険検知・エラー防止」スキルを高める取組み
- 現場社員(運転士)の持つ「危険検知・エラー防止」スキルに注目
- 上記スキル(暗黙知)の抽出・共有および新たな発見を支援する方法の試作
- 成功を確実にする手法(Safety-Ⅱ)としての応用を計画
船舶の事故事例を活用した教育・訓練
- 船舶運航の概要
- 事故事例を活用した教育・訓練
- 教育・訓練の評価と効果のレビュー
ジェームズリーズンは、著書「組織安全」の中で、安全への取り組みは、「最後の勝利なき長期のゲリラ戦である」と例えています。Human Errorへの取り組みは、まさにこのとおりです。To Error is Humanといわれるように、新人であれ、ベテランであれ、Human Errorを起こすことはあり、Human Errorをゼロにすることはできません。では、Human Errorへの取り組みで、我々にできることは何があるのでしょうか? Human Errorを起こしにくくする仕組み作り、Human Errorの影響を小さくする仕組み作り、あるいはHuman Errorを起こしそうな状況にいち早く気づき、対応すると取り組みということになります。Human Errorを起こすような状況にいち早く気付き、対処していくというのは簡単ですが、どうすれば、そのようなスキルが身につくのでしょうか? 今回、東日本旅客鉄道㈱ならびに川崎汽船㈱で行われている、危険や不安全な状況に気づき、対応するスキルを身につけることを目的とした取り組み(教育訓練)についてご紹介いただきます。この取り組みが、皆様のご参考になれば、幸いです。
2020年2月21日(金)
10:00~17:00
S7
産業安全と安全教育 ~一人一人を逞しく育てる
このセッションはパネルディスカッションとなります。
事例発表者と参加者の皆様との交流を図ることを目的とします。
事例発表者と参加者の皆様との交流を図ることを目的とします。
産業安全教育の体系化と共有化を考える
- 体系的安全教育プログラムの構築と推進
- 産業安全教育の体系化と共有化
- 学校安全教育の現状と課題
鍛える! ~歴史の中で「退化」したもの
- 製造業の歴史を振り返る
- 標準化の功罪
- 「考える力」を取り戻す!
産業安全塾の取組み
~安全のわかる将来の経営層の育成を目指して
~安全のわかる将来の経営層の育成を目指して
- 産業安全塾の目的と歴史
- 協会保安行動計画における産業安全塾の位置づけ
- 産業安全塾の具体的内容紹介
産業安全行動分析学への招待
- 危険感受性を育てるには何が有効か~応用心理学の観点からの考察
- 行動分析の紹介と安全行動への応用~「産業安全行動分析学」
- 価値観を変える~ヒヤリハットは忌むべきものではなく喜ぶべきもの
機械システム安全研究グループ 主任研究員
トヨタの”安全な人作り” ~トヨタにおける現場第一線メンバーの安全力育成
- 安全教育の振返りとこれからの教育の在り方
- 「モノづくりは人づくり」を実践する考えて行動できる人づくり
- 一人ひとりの心に響く安全研修の取組み
体感教育の実際 ~三井化学技術研修センターの取組み
- 三井化学技術研修センターの取組み紹介
- 技術伝承教育の課題と対応
- VRを活用した出前研修の紹介
海外巨大プロジェクトにおける多国籍労働者の安全教育とその効果
- 海外石油ガスプロジェクト建設工事の安全管理について
- 多国籍労働者への教育と課題
- 安全文化の構築と教育の相乗効果
「最近、「考えない人間」が増えたよなぁ」こんな声が皆さんの職場でも聞かれませんか? 我々は、製造技術や設備技術、IT技術などを進化させ、製造現場を革新してきました。一方で、標準化を進め、誰でも同じように作業ができるように効率化も実践してきました。また、管理者には成果達成を求め、文書による報告を求めてきました。その結果、この裏返しとして、一人一人に対し「「考える」ことの育成」を忘れ、「考える」力や習慣を奪ってしまったのではないでしょうか? 安全現場を見ると、大災害の多発や繰り返しは確かに激減していますが、全産業を通じ年間で見ると、大災害の発生や現場第一線での微小災害やヒヤリ事例はゼロ化できず、この撲滅に、日々、追われていないでしょうか? なぜ、このような事態に陥っているのか? 今回のセッションでは、まず、その原因を紐解き、実際の現場の課題を整理します。そして、経営層、管理者から現場第一線まで、一人一人の役割に立ち返り、如何なる力を蘇生すべきか、実際にどのような手段で鍛えるか、さらには行動心理学の側面から「育成」を考えてみます。参加者皆様には、このセッションで学んだことを自分の職場に持ち帰り、「逞しい人材」の育成を、是非、考え実践して頂きたいと思います。
プログラム内容(講演テーマ・スピーカ・パネリスト・講演の順番等)は変更になる場合がありますので予めご了承ください。