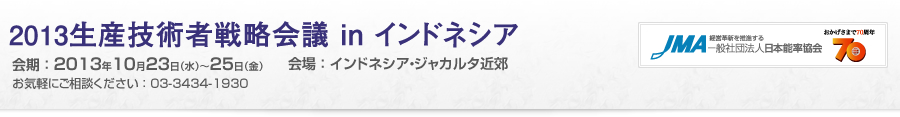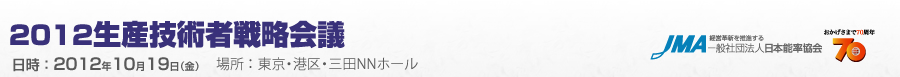特別インタビュー(3) その3
「国内外生産比率と内外作区分」 |
|||
 |
安部武一郎 一般社団法人日本能率協会 |
野元伸一郎 日本能率協会 コンサルティング シニア・コンサルタント (敬称略) |
 |
特別研究セッションの「聴きどころ」を日本能率協会の安部武一郎がインタビューする3回目です。コーディネーターの野元伸一郎氏がパネリストから引き出す「これからの生産技術者の役割」の聴きどころをどうぞ!
-今回は聴きどころの3回目で「国内外生産比率と内外作区分」というテーマです。
-生産技術者戦略会議の特別講演Ⅰでは富士ゼロックスの渡部さんにお話いただきます。
富士ゼロックスさんは、部品の外部生産委託をされたことがあったそうです。
-ところが低コストだけれども、情報と技術が外に出て行った結果、設計にフィードバックができなくなって、スピードあるモノづくりが難しくなったということがあり、その要因を分析した結果、主要なものは社内で作れるはずだという決断を経営トップがされたそうです。
-とはいっても、一度外に出したモノを元にもどすのは簡単ではありませんよね。
-その経験を渡部さんの特別講演でお話いただけることを期待しています。
-この特別講演を受けてパネルディスカッションではどのあたりが聴きどころになりますか?
-外に出したモノをもう一度、社内に戻すという歴史というか、経験は参考になりますよね。
-生産技術者戦略会議の特別講演Ⅰでは富士ゼロックスの渡部さんにお話いただきます。
富士ゼロックスさんは、部品の外部生産委託をされたことがあったそうです。
-ところが低コストだけれども、情報と技術が外に出て行った結果、設計にフィードバックができなくなって、スピードあるモノづくりが難しくなったということがあり、その要因を分析した結果、主要なものは社内で作れるはずだという決断を経営トップがされたそうです。
-とはいっても、一度外に出したモノを元にもどすのは簡単ではありませんよね。
-その経験を渡部さんの特別講演でお話いただけることを期待しています。
-この特別講演を受けてパネルディスカッションではどのあたりが聴きどころになりますか?
-外に出したモノをもう一度、社内に戻すという歴史というか、経験は参考になりますよね。
内外作区分を考える、ということを過去の歴史に学ぶという観点は非常に重要ですね。
ただ、もうひとつは、どの部分を出してしまったら二度と戻ってこないのか。ということを考える必要があるでしょうね。
ODM / EMSを使うにしろ、どこは絶対出さないというポリシーが重要になります。そのポリシーは経営トップだけが決めるのではなくて、現場発で「残さなくちゃいけない」と、経営トップにアピールしなければならない。
それは、部品メーカーだけでなく、セットメーカーであっても、残さなくちゃいけないというポリシーをきちんとしなきゃいけない、そういう曲がり角にきていると思います。
ただ、もうひとつは、どの部分を出してしまったら二度と戻ってこないのか。ということを考える必要があるでしょうね。
ODM / EMSを使うにしろ、どこは絶対出さないというポリシーが重要になります。そのポリシーは経営トップだけが決めるのではなくて、現場発で「残さなくちゃいけない」と、経営トップにアピールしなければならない。
それは、部品メーカーだけでなく、セットメーカーであっても、残さなくちゃいけないというポリシーをきちんとしなきゃいけない、そういう曲がり角にきていると思います。
-内外作区分の観点では、技術、コスト、リードタイムなどさまざまなありますよね。
複合的観点で考えなければいけないでしょう。
海外でつくれば、コストを安くなるけれどもリードタイムは長くなりますし。
コア技術も自分達で考えるのとお客さん、競合がみているコア技術は違うと思うんですよ。
例えば、技術ならキーパーツということになるし、リードタイム短縮ならならモジュール化して競合と一緒につくっちゃえとか。
海外でつくれば、コストを安くなるけれどもリードタイムは長くなりますし。
コア技術も自分達で考えるのとお客さん、競合がみているコア技術は違うと思うんですよ。
例えば、技術ならキーパーツということになるし、リードタイム短縮ならならモジュール化して競合と一緒につくっちゃえとか。
-その判断はだれがするんでしょうか?経営トップがするんですよね。
確かに経営トップがする面もありますけど、設計、製造もわかる生産技術者が重要な役割を果たすでしょうね。
内外作区分とコア技術の残し方とそれを生産技術者が提案をしていかなきゃいけない。
そこでは生産技術ならではの視点というのがありますね。 そのひとつが、例えば「社内に戻ってこられるか」「一度だしたら戻すが難しいものは何か」という視点ですね。
内外作区分とコア技術の残し方とそれを生産技術者が提案をしていかなきゃいけない。
そこでは生産技術ならではの視点というのがありますね。 そのひとつが、例えば「社内に戻ってこられるか」「一度だしたら戻すが難しいものは何か」という視点ですね。
-なるほど、「戻ってこられるかどうか」は、現場発でないとわからないですね。
そういう生産技術起点の視点はいくつかあると思います。
業種業態によってユニークなものもあるかもしれません。
デンソーさんの場合は、マーケット立地という意味もあってグローバル拠点化がすすんでいますが、生産技術者の視点は、国内外生産比率の意思決定にも重要な役割を果たしていると思います。
この生産技術者戦略会議の特別研究セッションでは各社さんの「国内外生産比率と内外作区分」について聴いて、整理してみようと思っていますので、参加された方にそれを持ち帰って自社に応用してもらえたら嬉しいですね。
業種業態によってユニークなものもあるかもしれません。
デンソーさんの場合は、マーケット立地という意味もあってグローバル拠点化がすすんでいますが、生産技術者の視点は、国内外生産比率の意思決定にも重要な役割を果たしていると思います。
この生産技術者戦略会議の特別研究セッションでは各社さんの「国内外生産比率と内外作区分」について聴いて、整理してみようと思っていますので、参加された方にそれを持ち帰って自社に応用してもらえたら嬉しいですね。
-ありがとうございました。
生産技術者戦略会議は2012年10月19日開催です。ぜひ、「これからの生産技術者の役割」のディスカッションにご参加ください。生産技術者戦略会議は2012年10月19日開催です。ぜひ、「これからの生産技術者の役割」のディスカッションにご参加ください。 参加お申込みをお待ちしています
生産技術者戦略会議は2012年10月19日開催です。ぜひ、「これからの生産技術者の役割」のディスカッションにご参加ください。生産技術者戦略会議は2012年10月19日開催です。ぜひ、「これからの生産技術者の役割」のディスカッションにご参加ください。 参加お申込みをお待ちしています